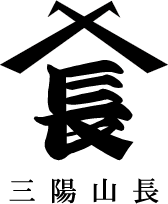ファッションエディターが見た
「いい靴」作りの流儀
十二.
作る責任、直す責任
一年間にわたって密着してきた、「いい靴」作りの流儀。その締めくくりに注目したいのは、本格靴を長く愛用するうえで欠かせないリペアのこと。魂を込めて作った一足だからこそ、一日でも長く履いてもらえるために修理にもベストを尽くす。そんなニッポン職人の心意気をご紹介します。

取材・文
編集者 小曽根 広光
三陽山長・商品企画担当の濱田さんから聞いて初めて知ったのですが、レザーソールは消耗が進んでくると水気に弱くなってくるのだそう。特に穴など空いてないけれど、ちょっと濡れた道を歩いだだけなのに足の裏がジットリ蒸れる……そう感じたら、そろそろオールソールのタイミングかも。
靴好き必修、リペアの心得
靴好き必修、リペアの心得
私が20代のころ、トラッド好き必携の某フランス靴が円高還元で大幅値下げされたことがありました。これぞ千載一遇の好機 ! と、当時の編集者仲間がこぞってショップへ急行。私もその後に続き、それからは嬉しさのあまり、ほとんど毎日履き倒しました。
同社の靴はラバーソールが驚くほど丈夫という噂のとおり、そんなハードユースにもかかわらずソールはピンピン。しかしよく見ると、つま先の出し縫い糸が数センチ切れていました。まあこれくらい問題ないだろうと、修理に出さずそのまま愛用。すると突然の豪雨に見舞われたある日、そこから大量に浸水して靴の中が水浸しに。肌へ吸い付くように柔らかかったライニングがカサカサになってしまい、早めに修理をしなかったのを大後悔したことがありました。これでは靴を作ってくれた職人さんたちにも申し訳ない。以来、“正しいリペアは靴を履く者の責任”と肝に命じています。
さて、リペアといって多くの方が気になるのは、“どこに依頼するか”ということでしょう。非常に優れた技をもつリペアショップも数々台頭していますが、やはりブランド純正の修理なら絶対安心です。使う部材はもちろん、見た目の雰囲気に影響する縫い方のクセなども再現することで、そのブランド特有の美学までも再生することができるからです。当連載の最終回は、リペアの視点から三陽山長の流儀を見ていきましょう。
実録・こうして靴は蘇る
実録・こうして靴は蘇る



こちらは三陽山長の人気モデル「勇一郎」。お手入れを重ねながら丁寧に履き込まれているため、アッパーは非常にいい状態を保っています。しかし、底周りを見ると相応に消耗が進んでいることがわかるでしょう。つま先はもう少しで出し縫い糸が切れそうなところまですり減り、ヒールも非対称に削れてきています。傷んだところを部分的に修理することも可能ですが、今回は「オールソール」で全体をリフレッシュしようということになりました。靴底全体を新しく取り付け直す、本格靴ならではの修理です。

まず、アウトソールと中底を抜い合わせている出し縫い糸を切断し、バリバリと剥がしていきます。その様子を間近に見ていると、“これ、本当に元通りになるの……?”と少々心配になってきますが、もちろん大丈夫。

ソールを剥がしたら、残った出し縫い糸も丁寧に取り除き、新しいアウトソールを改めて縫い付けていきます。三陽山長が主力とするグッドイヤーウェルト製法の靴は、このようにアウトソールを付け直せるのが強み。それゆえ、10年、20年と履き続けられるのです。




アウトソールを付け直すということは、当然ヒールも作り直します。革を何枚も積み重ねて釘で打ち付け、革包丁で形を整え、何度もヤスリをかけて磨きあげていく。職人の手仕事がたっぷりと費やされます。

黒のインキで靴底とコバを仕上げたら、オールソールが完了 ! 底だけ見ると、まるで新品のようになりました。これでまた、安心して愛用することができます。


ちなみにオールソールを繰り返すと、中底とアウトソールをつなぐウェルトが傷んできます。その場合はウェルトも新たに付け直す「リウェルト」を行うことで修理が可能に。また、内部に仕込んだコルクにダメージが蓄積している場合、それも交換することもできます。
ゼロから作るより難しい!? ライニング修理の妙技
ゼロから作るより難しい!?
ライニング修理の妙技
ゼロから作るより難しい!?
ライニング修理の妙技

底周りが新品同様に生まれ変わったこちらの靴ですが、実はアッパーにも問題が。内側のライニングが摩擦によってすり減り、ペロンとめくれてしまっています。履き心地だけでなく見た目も不恰好ですが、こちらもリペアで復活させることが可能です。




ライニングの場合、アウトソールのように全体を交換……というわけにはいきません。傷んだところに当て継ぎをして修理をしていくわけですが、これがかなりの難度。足当たりが悪くならないよう歪みなくぴったりと継ぎ、見た目にも極力目立たないように仕上げなければなりません。さらに、継いだ部分はアッパーと縫い合わせる必要がありますが、これも元々のステッチと寸分違わず重ねて縫う必要があります。「正直、ゼロから作るよりも修理のほうが難しいんです」と、職人さんがポツリ。

ライニング修理が完成したところ。一見ではわからないほど綺麗に仕上げられています。三陽山長のステッチは非常に精緻なため、修理をするにも極めて高い技術が求められます。



こちらがリペアを終えた「勇一郎」。経年変化で味わい深く育ったアッパーの表情はそのままに、傷んだ箇所はピカピカになりました。三陽山長がリペアに込める流儀は、靴作りと同様にクオリティ・ファースト。手間ひまを惜しまず実直に作った一足だからこそ、修理にも決して手を抜かない。そんな信念がひしひしと伝わってきます。
ヴィンテージスチールは“履く前”につけるのが正解
ヴィンテージスチールは
“履く前”につけるのが正解
ヴィンテージスチールは
“履く前”につけるのが正解

ここからは少々話題を変えて、リペアにまつわるワンポイント・アドバイスを。靴底のなかでも最初に消耗しやすい部分といえばつま先ですが、ここに「ヴィンテージスチール」とよばれる金属のチップを装着することでそれを防止することができます。ちなみに、装着するなら靴を履き下ろす前が効果的。というのも、靴底のつま先部分は履き込むうちに上へカーブしていくため、次第に地面と擦れにくくなっていきます。つまり、最もつま先が摩耗しやすいのは新品のときなのです。
耐久性を高めるなら、
ハーフラバー装着もひとつの手
耐久性を高めるなら、ハーフラバー装着もひとつの手
耐久性を高めるなら、
ハーフラバー装着もひとつの手

アウトソールの広範囲をダメージから守りたいなら、「ハーフラバー」を後から到着するという手も。非常に薄いため、レザーソールのドレッシーな見た目をキープしつつ耐久性を高めることができます。水濡れに強くなり、靴底が滑りにくくなるのもメリット。




大きなダメージがなければ、少々履き込んだ靴底の上からハーフラバーを貼ることも可能です。装着面をヤスリで整えて接着剤でラバーを取り付けたら、アウトソールの形に合わせて丁寧に削り、靴へ馴染ませていきます。
さて、一年間続いた当連載もこれで終了。長きに渡りお付き合いいただき、誠にありがとうございました。これまでの仕事で何百足と本格靴を見てきたし、三陽山長のファクトリーを取材するのも初めてではないから、過去をおさらいして原稿にまとめればいいだろう……と連載当初は思っていたのですが、実際に改めて靴作りの現場を目にしてみると、驚かされる新発見が数え切れないほどありました。もとより断然革靴派な私ですが、やっぱり“いい靴”って最高だなぁと愛着を新たにした次第です。そして、来月からはテーマを変えて新章がスタート。この一年で学んだ色々な知識を活かしつつ、三陽山長チームとがっつり打ち合わせをしながら、私にとっての“理想の靴”をゼロから製作いたします ! ぜひ、引き続きご注目ください !
◀ PREV

NEXT▶